自由研究は終わりましたか?まだなら、さーゆかん!化石掘り!!
こんにちは🍀木更津市で◯◯◯を行っている歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニック🍀です。
夏休みの自由研究の宿題はもう終わりましたか。うちの子はまだという場合はさすがに親の手伝いが必要でしょう。低学年定番の朝顔などの観察日記の様な継続的な自由研究はもう時間がないので、一発ものの実験か工作になってしまいそうではありますね。
観察日記と言えば、私の場合「蚕」の成長観察日記を思い出します。

私の娘と息子の通っていた小学校は同じではありません。また年齢も10歳以上離れているので、学校でやる内容も指導要項の変化に伴い異なりました。しかし理科の生き物の観察はなぜか内容が一緒でした。もっと早い時期であれば、皆様のお子さんの自由研究のネタになったかもしれなかったのですが、タイミングが悪くてごめんなさい。それとも今でも小学校の理科の授業でやっているのでしょうか?
理科の授業で子供達は「蚕」を家庭に持ち帰らされました。幼虫から繭になるまでを観察するのです。ここで問題になるのが「蚕」の餌です。「蚕」は桑の葉しか食べません。

学校の先生は「桑の葉はよーく注意して道を歩くと見つかります」と簡単に言ってくれる。はじめのうちは全然見つけられなかったのですが、慣れてくると街路樹の根元や草むらの中からお目当ての葉を見つけられる様になりました。親だけスキルアップです。
息子の時の教訓を踏まえ、その後私は庭に桑を植えました。その為、娘の「蚕」飼育時は葉っぱを探しに行く必要はありませんでした。しかし私の中に悲しき習性だけは残り、今でも車で走りながら、道脇の桑の葉をついつい探してしまうのです。
桑は地図記号に桑畑があることから、昔はとてもポピュラーな木であったのでしょう。
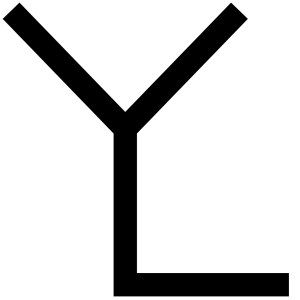
「蚕」の繭の糸は言うまでもなくシルクです。天然繊維の最高級品です。

日本の絹織物の歴史は古く、弥生時代に中国から技術が伝わったそうです。江戸時代には、商人が絹を手に取る機会もあったようですが、奢侈禁止令により一般庶民の絹織物の着用は制限されました。明治時代以降、絹織物は輸出産業として発展していったのでした。
横浜の大さん橋近くに「シルク博物館」があります。昔「蚕」を飼育した時に、関連したものとして子供の自由研究の為に訪れた事がありました。ここは絹織物の歴史を詳しく知る事ができます。また「横浜スカーフ」といわれる美しいシルクのスカーフも見れるので、親も楽しめました。(運良くさん橋に豪華客船が停泊していると更にテンションアップ!山下公園でも遊べる!)

また関連するものとして、世界遺産であり国宝である富岡製糸場に行って見るのも良いかもしれません。夏のお出かけと自由研究を一緒に終わらせてしまう事ができますよw
我が家では海水浴ついでに地層についての自由研究をした事もありました。崖の切り通しが見える海水浴場を選んで出かけたりもしました。海水浴ついでに崖の写真を撮って、家に帰ってから調べてまとめていましたね。地層の褶曲が見える場所が見つかればかなりポイントが高いです。地殻変動の考察もできますからね!
地層がはっきりと見える場所としては、千葉県銚子市の屏風ヶ浦や犬吠埼、神奈川県の城ヶ島が有名です。

海水浴という条件を外せば、地層を観察出来る場所はまだまだいっぱいあります。
地層と言えば、娘が化石発掘にハマっていた時がありました。私も何度か化石発掘につきあわされました。発掘した化石の時代や気候、古代生物について調べる自由研究も楽しいかもしれませんね。恐竜骨格の展示や化石発掘体験が出来る群馬県の「神流町恐竜センター」にはよく行きました。スタッフさんも親切で葉っぱの化石などを持ち帰りました。地層の岩を金づちで何時間もコンコン切り出すのは結構大変でしたが楽しい作業です。キャンプ場もあるみたいです。

我が家は行った事はありませんが、埼玉県松山市には「化石と自然の体験館」があり、ここでも化石発掘が出来るようです。どちらにせよ「地学」という科目は高校まではあるようなので、このような体験は損にはならないですよね。(私の行っていた高校は地学は選択必須でしたけど、今は選択できない高校もあるようですね。私は、なぜか地学Ⅱまでやったな〜!気象大学校を目指す子と一緒だったな〜!)せっかくなら自由研究をきっかけに様々な分野に楽しく興味を広げていってもらえたら親としても嬉しいですよね。
自由研究がまだ終わっていないご家庭はぜひ参考になさって下さい。テレビでも変わった自由研究特集を各局でやっていますよ!
7月に当院でも「歯医者さんの自由研究」を開催しました。残念ながら参加できなかったお子さんは、当院で歯科検診の予約をして、自分の検診の様子をリポートし、自由研究にしてみても良いかもしれませんね!検診と宿題の合わせ技です。

疑問に思った事はスタッフにどんどん質問してみましょう!


